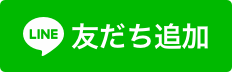伝統製法の本みりんは料理の味を高め、低GI値の優れた甘味料です。
料理に艶と甘みを加える「みりん」。和食には欠かせない調味料ですが、現在市販されているみりんの多くは、伝統的な本みりんとは大きく異なっています。「みりん風調味料」と「本みりん」、さらには本物の伝統製法のみりんの違いを知ることで、料理の味わいと健康、両方を高めることができます。今回は、みりんの選び方と活用法について詳しくご紹介します。
GI値(グリセミック・インデックス)は、食品が血糖値をどれだけ急速に上昇させるかを示す指標です。
ホンモノは美味しい
本来のみりんは、もち米を粕取り焼酎(日本酒の酒粕から造られた焼酎)と米麹で仕込み、1~3年ほど熟成させた発酵調味料です。アルコール度数は14度前後あり、昔はお屠蘇(とそ)として台所仕事をする人々の楽しみでもありました。飲んでも美味しい「お酒」としての品質を持っていたのです。
しかし、現在流通している多くは「みりん風味調味料」と呼ばれるもので、水飴やブドウ糖、デンプンの酸化液に化学調味料や酸味料を加えた製品です。あるいは雑穀を糖化・アルコール発酵させた調味液にアルコールと塩を添加したものもあります。アルコール度数は1%未満で、開封後カビが生えやすく、粘りつく甘味ともったりした単調な風味が特徴です。
「本みりん」と表示されている製品でも、伝統製法とは言えないものが多くあります。蒸したもち米と米麹を使っていても、アルコールや水飴を添加して2~3ヶ月という短期間で製造されたものが多く、本来のみりんより3~4倍に増量されていることもあります。原料の質や添加物の問題から、料理に使用しても本来の効果を発揮できないことが少なくありません。
おすすめは三河みりんなど、伝統製法で作られた本みりんです。料理にコクとうま味を与えるだけでなく、GI値(食後血糖の上昇を示す指標)が砂糖の2割程度しかなく、優れた甘味調味料としても活用できます。砂糖の代替品として上手に取り入れると良いでしょう。
みりんと漢方医学
みりんは漢方医学では「温性」で「脾胃」を温め、消化を助ける性質があります。特に伝統的な製法による本みりんは「気」を巡らせる効果があると考えられています。漢方では食物の持つ「気」を重視しますが、長期発酵させた本みりんには良質な「気」が宿るとされ、身体を内側から温める「温補」の効果があります。
漢方理論では、消化器系は「脾胃」と呼ばれ、食物からの栄養を吸収し「気血」を生み出す重要な役割を担っています。伝統的なみりんはこの「脾胃」の機能を高め、特に「脾虚」(消化吸収力の低下)や「胃寒」(胃が冷えている状態)に悩む人には適した調味料とされています。
また、みりんの適度な甘みは「脾」を強化し、消化吸収を促進する効果があります。一方で、化学添加物の多い「みりん風調味料」は漢方的に見ると「邪気」を招きやすく、本来の「気」を損なう可能性があります。
昔の薬膳では、みりんは「薬食同源」の考え方から冬季の「温補」や「気虚」の状態にある人の回復食に活用されていました。特に体を冷やす食材と組み合わせることで、その冷えを緩和する効果も期待されています。
伝統製法の本みりんは料理の味を高める上質な発酵調味料です。
三河みりんのような本物は、料理にコクを与えるだけでなく、低GI値の甘味料としても優れています。「みりん風調味料」とは全く別物です。漢方医学の観点からも、伝統的な本みりんは「脾胃」を温め、消化機能を高める優れた発酵食品といえるでしょう。
- 参考文献「食がもたらす病」ルネサンス vol.13 ダイレクト出版

第11回 畜産品(肉・牛乳・卵)

第10回 魚

第9回 野菜

【食養生シリーズ】第8回 豆腐

【食養生シリーズ】第7回 小麦

【食養生シリーズ】第6回 米

【食養生シリーズ】第5回 食用油

【食養生シリーズ】第4回 みりん

【食養生シリーズ】第3回 醤油

【食養生シリーズ】第2回 砂糖