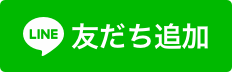玄米には発芽毒があり、長時間の浸水による無毒化が必要です。
日本人の主食である米は、他の食品と比較すると比較的安全な食材です。有機・無農薬栽培を選ぶことで、良質な米を手に入れることはそれほど難しくありません。しかし、健康志向で選ばれることの多い玄米には、知っておくべき重要なポイントがあります。
玄米は食べ方に注意
玄米を含む植物の種子には「発芽毒(酵素阻害剤)」が含まれています。これは土中での腐敗を防ぐため、種の周囲を保護する物質ですが、人間の健康にも影響を与える可能性があります。
発芽毒は虫や細菌だけでなく、人間の細胞内のミトコンドリアにも害を及ぼすことが分かっています。ミトコンドリアは代謝を司る重要な器官で、ここに悪影響が出ると、低体温、不妊、がんのリスク増加、さらには酵素の働きを妨げて免疫機能低下を招く可能性があります。
玄米を健康的に食べるには、この発芽毒を無毒化する必要があります。最も効果的な方法は、玄米を夏は12時間、冬は24時間浸水させることです。これにより発芽前の状態になり、発芽毒が代謝されます。
玄米を炒る方法もありますが、発芽毒は消えるものの、代わりにアクリルアミドという発がん物質が生成されるためおすすめできません。同様に、圧力鍋で炊く方法もアクリルアミドを発生させるため避けた方が無難です。
注意が必要なのは、市販の多くの玄米で浸水しても発芽しないものがあることです。これは高温での加熱乾燥によって種が死んでしまっているためで、浸水しても発芽毒は消えません。また、「発芽玄米」として売られている商品も、乾燥時に発芽毒が多量に産出されるので避けた方が良いでしょう。
米と漢方医学
米は漢方医学において「平性」で「脾胃」を養う基本食材です。特に日本人の体質に合った主食として「気血」を補い、エネルギーを生み出す源とされています。
白米は漢方では「温性」寄りで消化吸収がよく、「脾胃」の働きを助けるとされています。一方、玄米は「涼性」傾向があり、余分な熱を冷まし解毒作用があるとされますが、脾胃の弱い人や「寒証」の人(冷え症の人)は消化に負担がかかるため、浸水や発酵などの前処理が必要とされています。
漢方では「穀気」という概念があり、米にはこの「穀気」が豊富に含まれていると考えられています。「穀気」は人間の基礎的なエネルギーを作る元になるもので、特に「命門の火」(体の根本的な活力)を支える重要な要素です。
発芽毒を含む玄米をそのまま食べることは漢方的にも「傷脾」(脾を傷つける)行為とされ、特に「脾胃」の弱い人には避けるべきとされています。適切に浸水処理された玄米は「脾」を傷めず、むしろ「補脾」(脾を補う)効果があるとされています。
また、漢方では個々の体質に合わせた米の調理法や食べ方を重視しており、特に「命門の火」が弱い人には温かく炊いた米が推奨されています。
玄米は長時間の浸水が必須です。
天日干しまたは適切な温度管理で乾燥された発芽率の高い玄米を選び、しっかり浸水させてから調理しましょう。正しい食べ方を知ることで、玄米の栄養を安全に取り入れることができます。漢方医学的にも、適切に処理された玄米は体質に合った人にとって「気血」を補う優れた食材となります。
- 参考文献「食がもたらす病」ルネサンス vol.13 ダイレクト出版

第12回 加工肉

第11回 畜産品(肉・牛乳・卵)

第10回 魚

第9回 野菜

【食養生シリーズ】第8回 豆腐

【食養生シリーズ】第7回 小麦

【食養生シリーズ】第6回 米

【食養生シリーズ】第5回 食用油

【食養生シリーズ】第4回 みりん

【食養生シリーズ】第3回 醤油

【食養生シリーズ】第2回 砂糖