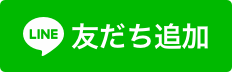現代の野菜は栄養価が低下しており、適切に育てられた野菜を選ぶことが重要です。
私たちが健康のために摂る野菜。しかし現代の野菜は昔に比べて栄養価が低下しているという問題があります。「食べている」と思っていても、本当に必要な栄養素が摂れていないかもしれません。
隠れた栄養不足の現実
地球上には満腹に食べているにもかかわらず、飢餓状態の人が20億人もいると言われています。これは単にカロリーが足りないのではなく、ビタミン・ミネラルといった微量栄養素が不足している「隠れ飢餓」の状態です。WHOや国際食糧政策研究所も警鐘を鳴らしている問題です。
野菜は本来、ビタミン・ミネラルの優秀な供給源ですが、様々な研究から、現代の野菜に含まれる栄養素が減少していることが分かっています。その原因は効率ばかりを重視した現代農法にあります。野菜をより大きく速く育てようとするあまり、栄養素が十分に生成されないまま収穫され、見た目は立派でも中身がスカスカになっているのです。
化学肥料の使用は土壌中の微生物にダメージを与え、土地を痩せさせます。さらに肥料の過剰使用は、深刻な健康被害を引き起こす可能性もあります。かつてアメリカで起きた「ブルー・ベビー事件」では、赤ちゃんにホウレンソウの裏ごしを与えたところ、顔色が青くなって死亡するという悲劇が起こりました。これは野菜に含まれる高濃度の硝酸塩が原因でした。
WHOは硝酸塩の単独致死量を4000mg、1日の許容摂取量を体重1kgあたり3.7mgと定めています(体重50kgの人なら185mg)。東京都の長期的な調査では、チンゲン菜から16000mg/kgという最大値が検出されました。計算上は250g(約1株半)で致死量に達する計算です。市販の野菜でも5000mg/kgレベルの硝酸塩を含むものは珍しくありません。
野菜と漢方医学
漢方医学の伝統的な考え方では、食材は色によって分類され、それぞれが体の異なる部分に作用すると考えられています。緑、赤、黄、白、黒の5色の食材をバランスよく摂ることで、体内の調和を保つという智慧があります。
五色の野菜と体への作用
緑色の野菜: ほうれん草、小松菜、ブロッコリー、きゅうり、アスパラガスなどの緑色野菜は、体の「肝」の機能と関連し、リラックス効果や体調を整える働きがあるとされています。春の季節と結びつき、体内の巡りを促進する性質があります。
赤色の野菜: トマト、赤ピーマン、ラディッシュなどの赤色野菜は、「心」の機能に対応し、活力を与える役割があります。夏の季節に関連し、血行を促進すると考えられています。
黄色の野菜: かぼちゃ、にんじん、とうもろこしなどの黄色野菜は、「脾」の機能を助け、消化を促進し、気分を明るくする効果があるとされています。土用(季節の変わり目)と関連し、栄養の吸収を助けます。
白色の野菜: 大根、かぶ、玉ねぎ、れんこんなどの白色野菜は、「肺」の機能に対応し、体内の不要なものを排出し、清浄にする働きがあります。秋の季節に関連し、潤いを与える効果があります。
黒色の野菜: 黒豆、しいたけ、ごぼう、ひじきなどの黒や濃い紫色の食材は、「腎」の機能を助け、体の基本的なエネルギーを蓄える役割があるとされています。冬の季節と関連し、温めて滋養する効果があります。
この考え方によれば、これらの色の野菜には体のエネルギーを高める効果があるとされ、栄養豊富な野菜は体の巡りを良くするとされています。特に旬の野菜や丁寧に育てられた野菜には豊かな栄養素が含まれているとされ、これは現代の栄養学の観点からも理にかなっています。
東洋の伝統医学では「医食同源」という考え方があり、日々の食事選びが健康維持に直結すると考えられてきました。質の高い野菜を選ぶことは、この伝統的な養生法の重要な要素といえるでしょう。
栄養豊富な野菜を見極める目を持ちましょう。
適切な肥料管理がなされ、丁寧に育てられた野菜を選ぶことが大切です。単に「有機」というラベルだけでは、どのように作られたかを判断するのは難しいため、真摯に農業に取り組んでいる生産者を探すことが重要です。東洋医学では、五つの色(緑、赤、黄、白、黒)をバランスよく摂ることで体内の調和を保つという考え方があります。これらの色の野菜をまんべんなく取り入れた食事と、質の高い野菜選びが、健康維持の基本と考えられています。
- 参考文献「食がもたらす病」ルネサンス vol.13 ダイレクト出版

第12回 加工肉

第11回 畜産品(肉・牛乳・卵)

第10回 魚

第9回 野菜

【食養生シリーズ】第8回 豆腐

【食養生シリーズ】第7回 小麦

【食養生シリーズ】第6回 米

【食養生シリーズ】第5回 食用油

【食養生シリーズ】第4回 みりん

【食養生シリーズ】第3回 醤油

【食養生シリーズ】第2回 砂糖